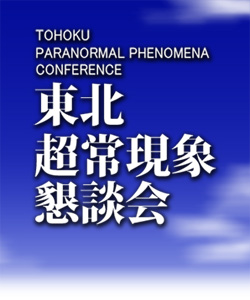 |
|
|
よくある質問 |
|
Q.
|
「お化け」「幽霊」「妖怪」ってどう違うの? |
| A. |
「お化け」「幽霊」「妖怪」には区分があります。 ●お化け お化けは「人間以外のものが変化したもの」だそうです。タヌキが化けたものや、傘が化けたりしたものですね。 ●幽霊 人の霊魂です。いちばん怖く感じるのは、主にこの幽霊のことではないでしょうか? ●妖怪 この分類が一番難しいかもしれません。傘がモチーフの「からかさお化け」などという名前の妖怪もいるし、「お化け」との区別は微妙なところですが、これらを分ける大事なポイントは、【怪奇現象を起こすかどうか】というところです。「からかさお化け」が何もしなければ、お化けに当たります。「小豆洗い」は、うるさい音を立てるので妖怪。足などに切り傷を付ける「かまいたち」も妖怪。 ちなみに、亡くなった子供の幽霊である「座敷童(ざしきわらし)」は、人間に干渉し幸運をもたらすとされています。つまり、「幽霊だけど妖怪」ということですね。
|
|
Q.
|
なぜ日本の幽霊に足がないの? |
| A. |
江戸時代に「幽霊絵画」で大評判だった、丸山応挙がそのルーツです。それ以前の幽霊画にはちゃんと足が書いてあります。
|